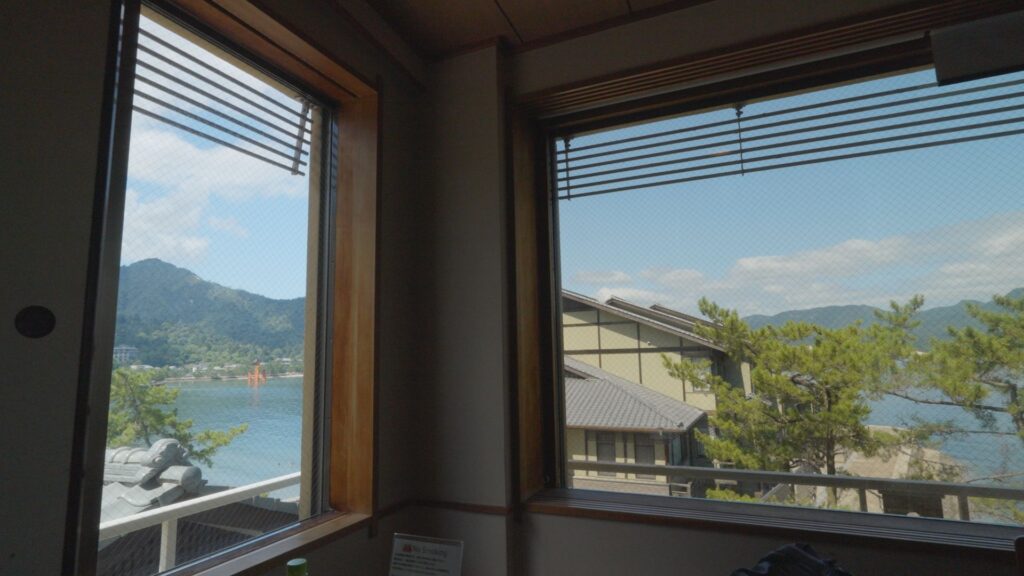ハルは、その日もいつものように、寂れた商店街のアーケードの骨組みに止まっていた。ドバトである彼が、なぜこれほどまでに人間の営みに興味を持つのか、他のハトたちには理解できないだろう。彼らにとって、世界はパンくずと交尾と、時折飛来するカラスとの攻防で成り立っている。だが、ハルは少し違った。彼は、通りを行き交う人間たち、特に「路地裏の住人」と彼が呼ぶ若者たちの出す音、彼らがまき散らす奇妙な熱気に、ある種の魅力を感じていたのだ。
路地裏の壁には、スプレーで意味不明な記号や、怒りにも似た文字が描かれている。ハルはそれらを、ハト同士の求愛ダンスのようなものだと解釈していた。つまり、彼らなりの「何かを伝えたい」という衝動なのだろう、と。
今日もまた、その路地裏に若者たちがたむろしていた。彼らはみんな、同じような薄汚れたTシャツを着ていて、髪の色だけが信号機のようにバラバラだった。彼らが吸うタバコの煙は、ハルの羽を燻すには十分すぎるほどだったが、彼は動かなかった。彼らはいつも、意味もなく笑い、叫び、そして壁を蹴った。ハルには、彼らの会話の内容は理解できない。だが、彼らが発する音の「質感」は、よくわかった。それは、乾いた葉っぱが風に吹かれるような音ではなく、まるで古いモーターが錆びついた中で回っているような、どこかぎこちなく、苛立ちをはらんだ音だった。
「なぁ、この町はクソだ」
一人の男が、壁に寄りかかりながら言った。彼は、まるで喉に小さな棘が刺さっているような声を出した。ハルは、彼を「棘」と呼ぶことにした。
話しかけられた方の男は、長い前髪で目を隠している。彼からは、いつもタバコと、諦めにも似た匂いがしていた。ハルは彼を「煙」と呼んだ。
「ああ、クソだ」煙は短く答えた。「どこへ行っても同じだし、どこへも出られない」
ハルは首を傾げた。出られない?空はどこまでも繋がっているではないか。飛んでいけばいい。彼らに羽根がないから、そんなことを言うのだろうか。
彼らはよく、ギターという奇妙な形の木片を抱えていた。煙がそれを掻き鳴らすと、耳をつんざくような、しかしどこか胸に響くような音がした。それは、ハルが時折遭遇する、飢えた猫の威嚇の声よりも、もっと複雑な音だった。「死ね!クソッ!」と、彼らが叫ぶと、ハルの心臓はわずかに跳ねた。それは、人間が発する音にしては、あまりにも純粋な、怒りの塊だったからだ。
ある日、一人の少年が路地裏に現れた。彼は、他の若者たちよりも少し幼く、そして目が澄んでいた。ハルは彼を「レンズ」と呼んだ。レンズは、他の若者たちが壁にスプレーで文字を書いているのを、じっと見ていた。やがて、彼は震える手で、ポケットから小さな石を取り出した。そして、その石で壁のコンクリートを掻き始めた。カツ、カツ、と小さな音がする。彼は、何かを懸命に、しかし不器用に書きつけようとしているようだった。
「おい、何してるんだ」棘が言った。
レンズは顔を上げず、ただひたすら石で壁を削っていた。やがて、そこには、歪んだ線で描かれた、奇妙なものが浮かび上がった。それは、人が両手を広げて、空を見上げているような絵だった。しかし、その人の頭には、まるで光の輪のように、いくつかの小さな円が描かれていた。ハルには、それが何を意味するのかわからなかった。だが、その絵からは、彼が以前に感じたことのない、「何とかしたい」という、切実な願いのようなものが伝わってきた。
「なんだ、あれ」煙が言った。「聖者か何かか?」
レンズは何も言わず、ただその絵をじっと見つめていた。彼の目には、絶望と、しかしごくわずかな、何かを信じようとする光が宿っているように見えた。ハルは、その絵と、その少年の姿から、彼らがただ怒っているだけでなく、何か別のものを求めていることに気づいた。それは、パンくずや交尾では満たされない、もっと根源的な、そして切実な渇望だった。
ハルは、彼らが「クソな日常」と呼ぶものを理解できた。それは、彼が毎日見る、同じ商店街のアーケード、同じ時刻に通り過ぎる列車、そして同じように意味なく飛び回る他のハトたちと、どこか似ていた。ただ、人間には、それを「クソだ」と感じ、そして叫ぶことができる言葉と苛立ちがあった。そして、その苛立ちの先に、彼らは、レンズが描いたような、救いを求める聖者のような存在を、無意識に探し求めているのかもしれない。
ハルは、その日も路地裏の若者たちを観察し続けた。彼らがいつか、その聖者を見つけるのか、それとも別の叫びを見つけるのか、ハルには知る由もない。だが、彼は、若者たちの奇妙な熱気と、どこか悲しい叫びを聞き続けるだろう。なぜなら、それが、この退屈な世界で、彼自身が唯一飽きずに続けられる、ささやかな探究だったからだ。そして、彼は知っていた。世界は、彼らが啄むパンくずよりも、はるかに広大で、複雑で、そして時に理不尽なものであることを。
人間の、あまりにも人間的な感情の機微を、ハルは今日も、アーケードの骨組みから見つめている。